はじめに:清掃業における公共調達の可能性
近年、多くの業界でビジネス環境が大きく変化する中、安定した収益源を確保することは、企業経営における最重要課題の一つです。特に、私たち清掃業界においては、価格競争の激化や人材不足といった課題に直面しており、新たな事業の柱を模索している経営者の方も少なくないでしょう。
そのような状況下で、今、大きな注目を集めているのが「公共調達(官公庁入札)」という市場です。国や地方自治体、独立行政法人などが発注する清掃業務は、景気の波に左右されにくく、一度契約を獲得すれば長期間にわたって安定した収益が見込めるという大きな魅力があります。
しかし、その一方で、「入札は手続きが複雑で難しそう」「うちのような中小企業には縁のない話だ」といったイメージから、参入をためらっているケースも多いのではないでしょうか。
本記事では、そうした疑問や不安を解消し、清掃業者が公共調達市場へ参入するための具体的な道筋を明らかにしていきます。具体的には、以下の3つのポイントを深掘りしていきます。
- 参入の鍵となる「建築物清掃業登録」制度の徹底解説
- 数億円規模の案件も!実際の入札案件から見る市場の実態と規模
- 「資格」「実績」といった参入障壁の正体と、それを乗り越えるための具体的な戦略
この記事を読み終える頃には、公共調達がもはや「未知の領域」ではなく、自社の成長戦略に組み込むべき「具体的な選択肢」となっているはずです。安定した経営基盤を築き、企業の新たな未来を切り拓くための一歩を、ここから踏み出しましょう。
2. 「建築物清掃業登録」とは?参入の第一歩を徹底解説
公共調達市場への扉を開く上で、まず理解しておくべき重要な制度が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に基づく「事業登録制度」です。特に清掃業においては、「建築物清掃業(1号登録)」が、入札参加における信頼性や専門性を示す上で極めて重要な役割を果たします。
制度の概要:なぜこの登録が必要なのか?
この登録制度は、建築物の衛生環境を維持管理する事業者の資質向上を目的として、1980年(昭和55年)の法改正により設けられました。国が「この事業者は、専門的な清掃業務を適切に行うための基準を満たしています」とお墨付きを与える制度、と考えると分かりやすいでしょう。
登録は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行い、審査を経て認められます。有効期間は6年間で、継続して登録を維持するためには更新手続きが必要です。
登録は義務か?登録しないとどうなる?
ここで重要なのは、この登録は法的な義務ではないという点です。つまり、登録を受けていない事業者が清掃業務を行うこと自体は、何ら法律に違反するものではありません。
しかし、公共調達の世界では、この「登録の有無」が大きな意味を持ちます。多くの入札案件において、建築物清掃業の登録は、入札参加資格の必須要件、あるいは評価項目の一つとして設定されています。特に、学校、庁舎、病院といった大規模で衛生管理が厳しく求められる施設の案件では、登録業者であることが実質的な最低条件となるケースがほとんどです。
登録は、単なる手続きではなく、競合他社との差別化を図り、官公庁からの信頼を勝ち取るための戦略的な「武器」となるのです。
登録の要件:何をクリアすればいいのか?
では、具体的にどのような基準を満たせば登録を受けることができるのでしょうか。要件は大きく分けて「物的要件」「人的要件」「その他の要件」の3つに分類されます。
物的要件:最低限必要な機材
建築物清掃業(1号登録)に求められる機材は、驚くほどシンプルです。
- 真空掃除機
- 床みがき機
これら2種類の基本的な清掃機材を保有していることが、まず第一の条件となります。比較的小規模な投資でクリアできる要件と言えるでしょう。
人的要件:最重要ポイント「清掃作業監督者」
登録における最大のハードルであり、最も重要なのがこの「人的要件」です。具体的には、事業所に「清掃作業監督者」の資格を持つ者を置かなければなりません。
清掃作業監督者となるためには、以下のいずれかの要件を満たした上で、厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了する必要があります。
- ビルクリーニング技能検定(1級または単一等級)に合格した者
- 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
特に「ビルクリーニング技能検定」は、清掃作業の専門知識と技能を証明する国家資格であり、この資格を持つ人材を確保または育成することが、登録への鍵となります。また、監督者だけでなく、実際に作業に従事する者も、専門的な研修を修了している必要があります。
その他の要件
上記の他に、作業方法や機材の維持管理方法などが、法令で定められた基準に適合している必要があります。これには、適切な洗剤の使用方法、作業員の安全管理、機材の定期的なメンテナンスなどが含まれます。
参入障壁としての登録制度
ここまで見てきたように、建築物清掃業登録は、特に「清掃作業監督者」という人的要件において、一定の参入障壁となっています。しかし、見方を変えれば、この障壁があるからこそ、安易な価格競争に陥ることなく、技術力や専門性を持つ事業者が正当に評価される市場が形成されているのです。
次の章では、この登録制度をクリアした先にある、具体的な入札案件の世界を見ていきましょう。
3. 【案件ベースで分析】清掃業の入札案件、その実態と規模
建築物清掃業の登録という第一関門を突破した先には、どのような案件が待っているのでしょうか。ここでは、実際の入札案件をベースに、清掃業の公共調達市場の規模と実態を明らかにしていきます。
大規模案件の実例:3年で2.2億円!さいたま新都心合同庁舎の衝撃
まずご覧いただきたいのが、財務省関東財務局が発注した「さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務(清掃業務)」の案件です。
【案件概要】
- 落札者: 株式会社新東美装
- 落札金額: 221,400,000円(税抜)
- 契約期間: 令和5年4月1日~令和8年3月31日(3年間)
- 年間金額: 約7,380万円
- 入札方式: 民間競争入札

3年間で2億円を超えるこの案件は、清掃業の公共調達がいかに大規模な市場であるかを示す象徴的な事例です。年間約7,380万円という安定した収益は、企業の経営基盤を根底から支える力を持っています。この入札には7者が参加しており、最終的には価格で勝負が決まりましたが、参加するためには、同規模の施設の管理実績や、高度な品質管理体制が求められたことは想像に難くありません。
中規模・小規模案件の実例:地域に根差した安定収益源
数億円規模の案件は魅力的ですが、もちろん、より参入しやすい規模の案件も数多く存在します。
【宮崎県高鍋総合庁舎清掃業務委託】
- 落札者: 株式会社栄建工業
- 落札金額: 8,790,000円(税抜)
- 入札方式: 一般競争入札(条件付)
【札幌市中央図書館清掃業務】
- 落札者: ライラック興業株式会社
- 落札金額: 23,322,875円
これらの案件は、地域の庁舎や公共施設が対象であり、地元企業が受注するケースが多く見られます。年間数百万円から数千万円規模の案件を複数獲得することで、大企業にも負けない安定した収益ポートフォリオを構築することが可能です。
案件規模と要求される資格・実績の関係
これらの事例からわかるように、案件の規模が大きくなるほど、より高度な資格や豊富な実績が求められる傾向にあります。
- 大規模案件(数千万円~数億円): 建築物清掃業登録はもちろん、ISO9001(品質マネジメント)などの国際認証、同種・同規模業務の実績が必須条件となることが多い。
- 中規模案件(数百万円~数千万円): 建築物清掃業登録が評価を大きく左右する。地元企業であることが有利に働く場合もある。
- 小規模案件(~数百万円): 実績作りに最適。まずはこうした案件を確実に受注し、次のステップへの足掛かりとすることが重要。
契約期間と収益安定性
多くの清掃業務委託案件が、1年から3年の複数年契約となっている点も大きな魅力です。一度受注すれば、数年間にわたって安定した収益が見込めるため、経営計画が立てやすくなり、人材採用や設備投資も積極的に行えるようになります。
このように、清掃業の公共調達市場は、大規模な案件から中小企業が参入しやすい案件まで、多様な選択肢が存在する魅力的なフィールドです。次の章では、これらの案件を獲得するために乗り越えるべき「参入障壁」の正体と、その具体的な攻略法について解説します。
4. 参入障壁の正体と、それを乗り越えるための具体的な戦略
公共調達が魅力的な市場である一方、誰もが簡単に参入できるわけではありません。そこには、いくつかの「参入障壁」が存在します。しかし、これらの障壁は、乗り越えるための正しい知識と戦略があれば、決して高い壁ではありません。むしろ、競合をふるいにかけ、自社の強みを際立たせるための好機と捉えることができます。
障壁1:資格要件 - 公共調達へのパスポートを手に入れる
公共調達に参加するためには、まず「資格」という名のパスポートが必要です。
全省庁統一資格
国の機関が発注する入札に参加するためには、原則として「全省庁統一資格」の取得が必須です。これは、各省庁に共通で有効な資格であり、一度取得すれば、様々な官公庁の入札に参加できるようになります。申請はデジタル庁の「調達ポータル」から行い、納税証明書や財務諸表などの書類が必要となります。
建築物清掃業登録
前述の通り、これは法的な義務ではありませんが、事実上の「必須資格」です。特に地方自治体の案件では、この登録を入札参加の条件としているケースが非常に多く見られます。長崎市の例では、建物清掃業務の入札参加資格要件として、県知事の登録を明確に定めています。これは、業務の適正な履行を確保するための措置であり、今後この流れは全国的に加速していくと考えられます。
ビルクリーニング技能士
清掃作業監督者の要件ともなる国家資格「ビルクリーニング技能士」の存在も重要です。仙台市の入札説明書では、配置予定のビルクリーニング技能士が、入札参加申請者の被雇用者であることを証明する書類の提出を求めています。これは、単なる名義貸しではなく、実際に技術力のある人材が業務に従事することを担保するための要件です。
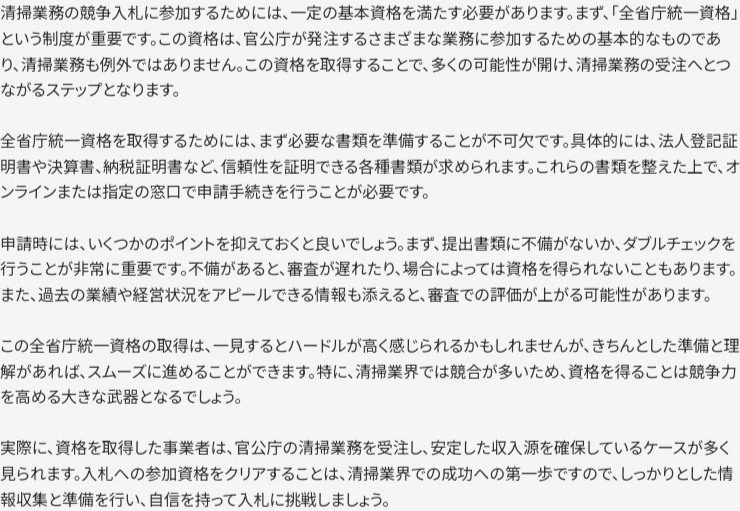
障壁2:実績要件 - 「鶏が先か、卵が先か」のジレンマを解消する
多くの入札案件で求められるのが「同種業務の実績」です。「実績がないから入札に参加できない、参加できないから実績が作れない」というジレンマは、多くの事業者が直面する壁です。
この壁を乗り越えるには、戦略的なアプローチが必要です。
- 小規模案件から始める:まずは、実績要件が比較的緩やかな小規模案件や、自治体の「オープンカウンター方式(見積合わせ)」などから始め、着実に実績を積み重ねていくことが王道です。
- 下請けとして経験を積む:元請けとして大規模案件を受注している企業の協力会社としてプロジェクトに参加し、経験とノウハウを蓄積するのも有効な手段です。
- JV(共同企業体)を結成する:実績のある同業者と共同企業体(JV)を組むことで、単独では参加できない大規模案件に挑戦することが可能になります。
障壁3:人的要件 - 技術力の中核を担う人材の確保
資格要件とも重なりますが、清掃作業監督者やビルクリーニング技能士といった専門人材をいかに確保し、育成していくかは、継続的に事業を拡大していく上で不可欠な要素です。資格取得支援制度を設けたり、働きやすい環境を整備したりするなど、長期的な視点での人材戦略が求められます。
障壁4:財務要件 - 安定した経営基盤の証明
入札に参加し、契約を履行するためには、安定した財務基盤も必要です。契約金額の10%程度に相当する「契約保証金」の納付や、業務の履行に必要な運転資金の確保、万が一の事故に備えた損害賠償保険への加入などが求められます。日頃から健全な財務体質を維持しておくことが重要です。
5. 明日からできる!清掃業の公共調達参入ロードマップ
これまで見てきた参入障壁を乗り越え、公共調達市場で成功を収めるための具体的な行動計画を4つのステップで示します。
ステップ1:情報収集 - 宝の地図を手に入れる
まずは、どのような案件が、いつ、どこで、どのような条件で発注されているのかを知ることから始まります。以下の情報源を定期的にチェックし、自社に合った案件を見つけ出す体制を構築しましょう。
- 調達ポータル(GEPS):国の機関の入札情報が一元的に公開されています。
- 各地方自治体のウェブサイト:都道府県や市区町村の契約課・管財課などのページを確認します。
- 入札情報サービスサイト:民間のサービスを利用し、効率的に情報を収集するのも有効です。
ステップ2:資格取得 - 武器を揃え、磨き上げる
情報収集と並行して、計画的に資格取得を進めます。
- 全省庁統一資格の申請準備を開始する。
- 自社の営業所がある都道府県の建築物清掃業登録の要件を確認し、申請準備を進める。
- 従業員のビルクリーニング技能検定の取得を支援し、清掃作業監督者を育成する。
ステップ3:実績作り - 小さな成功を積み重ねる
いきなり大規模案件を狙うのではなく、まずは受注しやすい案件で実績を作ります。
- 自治体のオープンカウンター方式(見積合わせ)に参加する。
- 実績要件の緩やかな小規模案件に積極的に応札する。
- 元請け企業との関係を構築し、下請けとしての実績を積む。
ステップ4:連携体制 - 力を合わせて大きな獲物を狙う
単独での参入が難しい場合は、他社との連携も視野に入れます。地域の同業者と情報交換を行い、信頼関係を築く中で、JV(共同企業体)の結成を検討し、中規模・大規模案件への挑戦の道を探ります。
6. まとめ:清掃業の未来は公共調達にある
本記事では、清掃業者が公共調達市場へ参入するための具体的な方法論について、登録制度、入札案件の実態、そして参入障壁の乗り越え方という観点から解説してきました。
一見、複雑に見える参入障壁は、裏を返せば、専門性を持たない安易な参入者を阻み、技術力と経営努力が正当に報われる健全な市場環境を生み出す「防波堤」の役割を果たしています。真空掃除機と床みがき機という基本的な設備からスタートでき、計画的な資格取得と実績の積み重ねによって、年間数千万円、さらには数億円規模の安定収益を目指すことができる。これこそが、清掃業における公共調達の真の魅力です。
今こそ、従来の価格競争から脱却し、専門性と品質で勝負する新たなステージへと歩みを進める時です。この記事が、皆様の企業の持続的な成長と発展の一助となれば幸いです。
参考情報
