司法書士向け入札案件!1,000万円超の長期相続登記等未了土地解消作業で落札を目指す入札参加ガイド
はじめに:司法書士の新たな巨大市場「長期相続登記等未了土地解消作業」とは?
2024年4月1日に施行された相続登記の義務化は、司法書士業界に大きな変化をもたらしました。個人のクライアントからの依頼が増加する一方で、これまであまり注目されてこなかった「公共調達」の分野、特に法務局が発注する「長期相続登記等未了土地解消作業」が、新たな巨大市場として急速に存在感を増しています。
この業務は、長期間にわたって相続登記がされていない土地の権利関係を、法務局の登記官に代わって調査し、法定相続人を特定するというもの。まさに司法書士の専門性がダイレクトに活かせる分野であり、その案件規模は、民間の個別の依頼とは比較にならないほどのポテンシャルを秘めています。
「公共調達は大手企業のもので、個人事務所には縁がない」 「入札なんて、手続きが複雑でよくわからない」
そう考えている方も多いかもしれません。しかし、この記事を読めば、その考えは大きく変わるはずです。本記事では、司法書士がこの新たな市場に参入し、事業の柱となりうる安定した高収益を得るための具体的な方法を、実際の落札実績や法務局の仕様書といった一次情報に基づいて、徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、以下のことが明確に理解できるでしょう。
- 1,000万円を超える案件が実在する市場の規模感
- 実際の仕様書から読み解く具体的な業務内容と参加資格
- ゼロから参入するための実践的なロードマップ
開業間もない方、新たな収益の柱を探している方、事務所の規模を拡大したい方。すべての司法書士にとって、この記事は新たな事業展開の扉を開く鍵となるはずです。
【衝撃】これが現実!1,000万円超えの落札実績を大公開
「本当にそんなに大きな案件があるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。まずは、論より証拠。近年、全国の法務局で実際に公告され、落札された「長期相続登記等未了土地解消作業」の具体的な実績をご覧ください。
| 発注機関 | 案件名 | 落札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大分地方法務局 | 長期相続登記等未了土地解消作業 | 約1,582万円 | 登記名義人470名分 |
| 長崎地方法務局 | 長期相続登記等未了土地解消作業 | 約2,465万円 | - |
| 和歌山地方法務局 | 長期相続登記等未了土地解消作業 | 約2,193万円 | - |
| 鹿児島地方法務局 | 長期相続登記等未了土地解消作業 | 約1,160万円 | - |
(出典:nSearch、各法務局公告情報)
表を見ていただければ一目瞭然ですが、1件あたり1,000万円、場合によっては2,000万円を超える規模の案件が、全国で多数発注されているのが現実です。
個人のクライアントから相続登記を1件受注した場合の報酬が、一般的に10万円前後であることを考えると、この公共調達案件がいかに桁違いのスケールであるかがお分かりいただけるでしょう。例えば、大分地方法務局の案件では、一度の受注で470名分の登記名義人に関する業務を行うことになります。これは、個別の顧客を一人ひとり開拓する営業活動とは全く異なる、まさに「スケールメリット」を享受できるビジネスモデルなのです。
一度の受注で、事務所の年間売上に匹敵する、あるいはそれを超えるほどのインパクトをもたらす可能性を秘めている。それが、「長期相続登記等未了土地解消作業」という市場の最大の魅力です。
【必読】実際の公告から読み解く!業務内容と参加資格
では、これほど大規模な案件を受注するには、具体的にどのような要件が求められるのでしょうか。ここでは、実際に福岡法務局が令和7年度に公告した「長期相続登記等未了土地解消事業(登記名義人200名分)の委託 一式」の入札公告を基に、その詳細を読み解いていきましょう。
ご要望にお応えし、実際の公告資料を掲載します。これにより、情報の信頼性を担保し、皆様が具体的なイメージを持てるようにします。
福岡法務局 入札公告(令和7年度)
以下は、実際に公告されたPDFのスクリーンショットです。
【1ページ目:入札公告の概要】 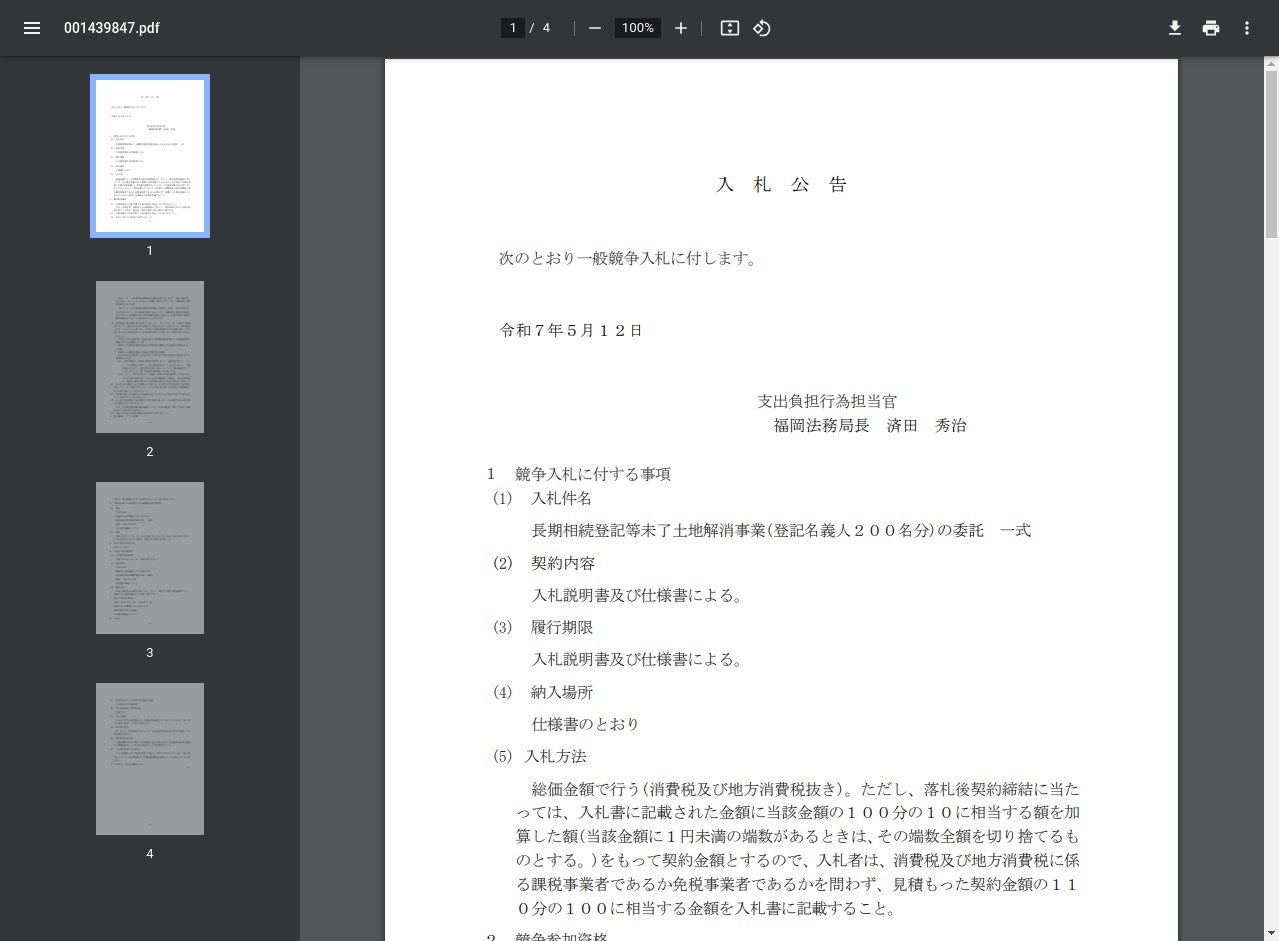 出典: 福岡法務局 入札・公募情報
出典: 福岡法務局 入札・公募情報
【2ページ目:競争参加資格】 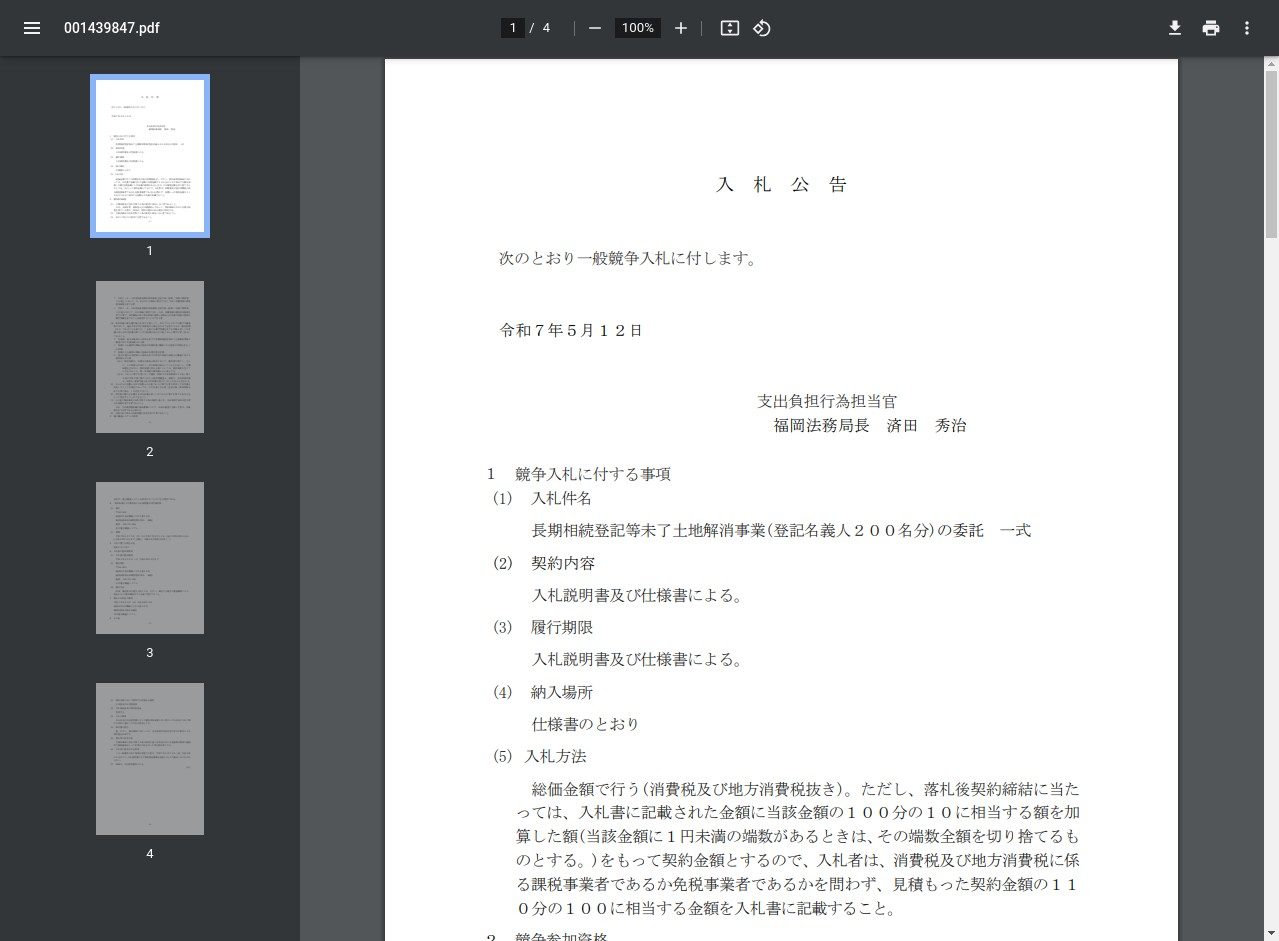 出典: 福岡法務局 入札・公募情報
出典: 福岡法務局 入札・公募情報
【3ページ目:入札手続等】 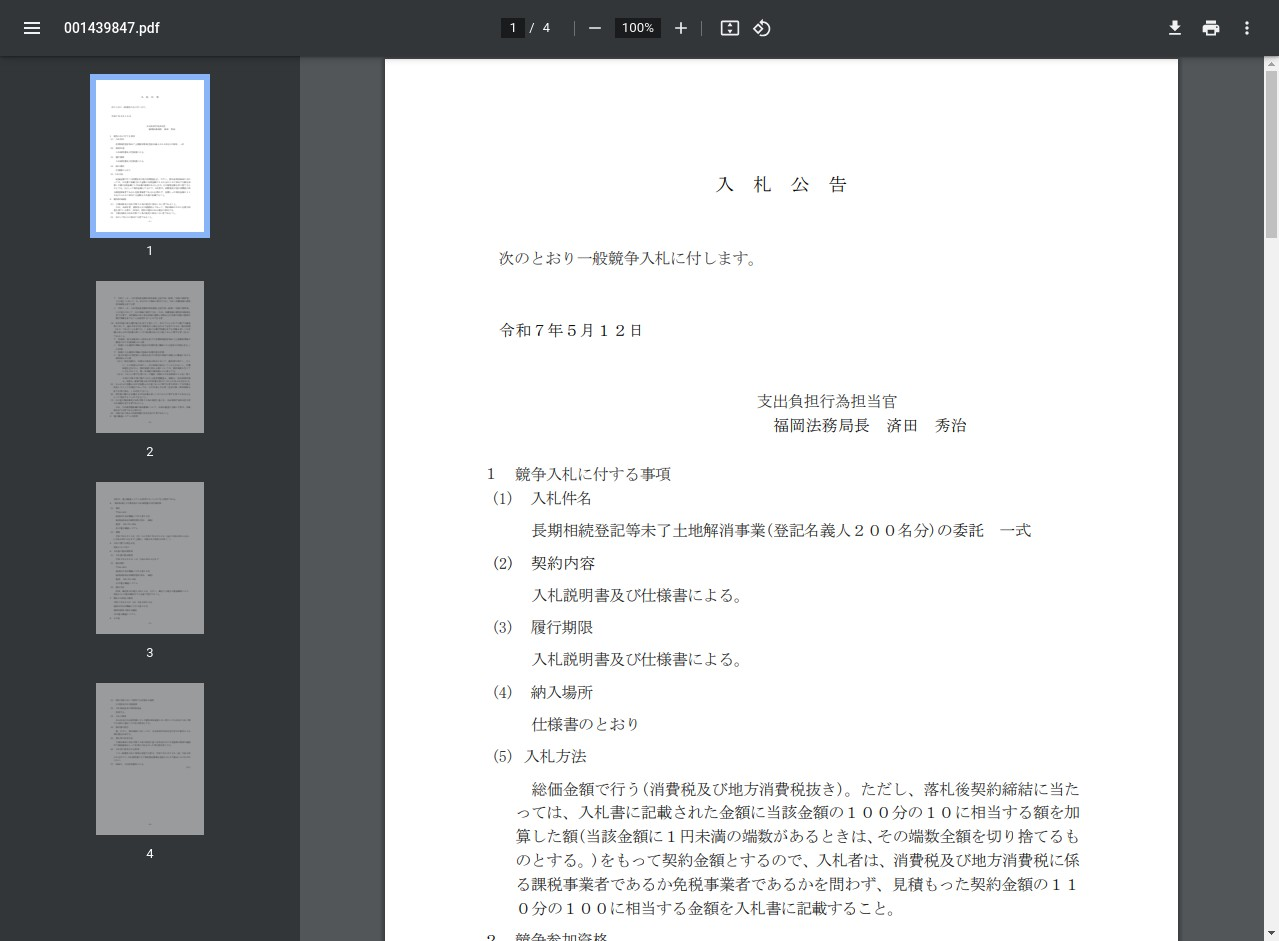 出典: 福岡法務局 入札・公募情報
出典: 福岡法務局 入札・公募情報
【4ページ目:その他】 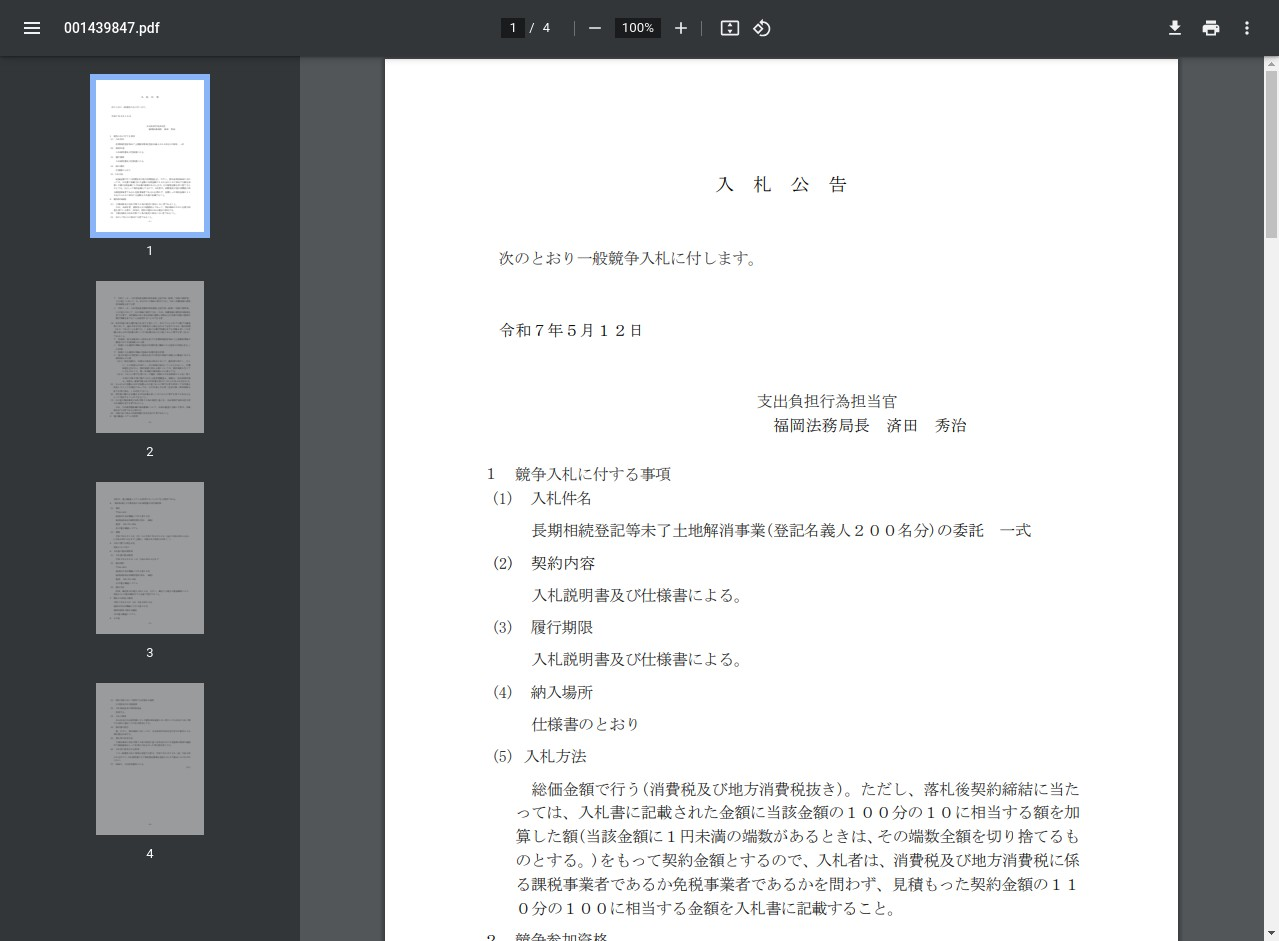 出典: 福岡法務局 入札・公募情報
出典: 福岡法務局 入札・公募情報
公告から読み解くポイント
この公告から、参入を目指す上で特に重要なポイントを3つ解説します。
1. 具体的な業務内容
仕様書には、具体的な業務内容として、登記名義人の法定相続人を特定するための戸籍調査や、その結果を取りまとめた法定相続人情報の作成などが記載されています。これはまさに、司法書士が日常業務で培っている専門知識とスキルそのものです。
2. 競争参加資格の核心:「15名以上の体制」
最も重要なのが、2ページ目に記載されている「競争参加資格」です。過去の同種案件の公告では、「本件業務に係る弁護士又は司法書士若しくはこれらに準ずる者15名以上をもって受託することができること」といった、人員に関する要件が課されていました。今回の公告でも同様の要件が課される可能性が非常に高いと言えます。
この「15名」という数字は、個人の事務所単独でクリアするには非常に高いハードルです。これが、この市場への参入を考える上で最も重要なポイントであり、共同受注(JV:ジョイントベンチャー)が事実上必須となる理由です。
3. 共同受注(JV)の必要性
JVとは、複数の事業者が共同で事業体を組織し、一つの案件を受注する形態です。この案件においては、複数の司法書士事務所が連携し、共同で提案・入札を行うことになります。JVを組むことで、1事務所あたりの人員負担を軽減し、大規模案件の受注に必要な体制を構築することが可能になります。
逆に言えば、強固なネットワークを持ち、信頼できる同業者とJVを組成できるかどうかが、この市場で成功するための絶対条件と言えるでしょう。
ゼロから始める参入ロードマップ
では、具体的にどのようにして、この魅力的な市場へ参入すれば良いのでしょうか。ここでは、明日からでも実践できる4つのステップに分けて、具体的なロードマップを提示します。
Step 1: 徹底的な情報収集
何よりもまず、敵を知ることから始めます。どのような案件が、いつ、どこで、どのような条件で発注されているのかを把握しなければ、戦略の立てようがありません。
- GEPS(政府電子調達システム): 国の機関の入札情報が掲載される公式サイトです。まずはここで、過去の公告や仕様書を検索し、業務内容や参加資格の傾向を掴みましょう。
- 民間の入札情報サイト: 「入札王」や「NJSS」といったサービスは、全国の自治体や公的機関の情報を網羅しており、キーワード検索やアラート機能が充実しています。「司法書士」「相続」「登記」といったキーワードで検索し、最新の案件情報を常にチェックする体制を整えましょう。
Step 2: 必須資格の取得
公共調達に参加するためには、まず「競争入札参加資格」を取得する必要があります。特に、国の機関の入札に参加するための「全省庁統一資格」は、法務局案件を狙う上で必須となります。申請手続きはオンラインで可能ですが、審査には一定の時間がかかるため、早めに準備に取り掛かりましょう。
Step 3: 小さな実績からのスタート
いきなり1,000万円級の案件を受注するのは現実的ではありません。まずは、地元の市区町村が発注する、より小規模な「空き家調査」や「相続人調査」といった案件から挑戦し、公共調達における実績を着実に積み重ねていくことが重要です。これらの案件は、数十万円から数百万円規模のものが多く、個人事務所でも十分に受注を狙えます。ここで得た実績と経験が、将来的に大規模案件に挑戦する際の強力な武器となります。
Step 4: 最も重要な「連携体制(JV)」の構築
前述の通り、大規模案件の受注にはJVの組成が不可欠です。日頃から、地域の司法書士会や研修、セミナーなどの場で、他の司法書士と積極的に交流し、信頼関係を築いておくことが何よりも重要です。
- 勉強会の開催: 有志で集まり、公共調達に関する勉強会や情報交換会を主催するのも良いでしょう。
- リーダーシップの発揮: JVでは、中心となって全体を取りまとめるリーダー役が必要です。積極的にリーダーシップを発揮し、案件獲得に向けて周囲を巻き込んでいく姿勢が求められます。
まとめ:チャンスを掴むために、今すぐ行動しよう
「長期相続登記等未了土地解消作業」は、司法書士にとって、これまでにない規模のビジネスチャンスをもたらす可能性を秘めた市場です。民間業務だけでは得られない安定性と収益性、そして社会貢献という大きなやりがいが、そこにはあります。
もちろん、参入にはJVの組成という高いハードルがあります。しかし、それは裏を返せば、行動を起こし、同業者との連携を密にした者だけが、この大きな果実を手にできるということです。
この記事を読んで、「面白そうだ」と感じたなら、ぜひ今日から行動を起こしてみてください。
- まずはGEPSにアクセスし、過去の仕様書を1件読んでみる。
- 次に、地元の司法書士会の会合で、公共調達に関心のある仲間を探してみる。
その小さな一歩が、あなたの事務所の未来を大きく変えるかもしれません。チャンスの扉は、行動する者のために開かれています。
